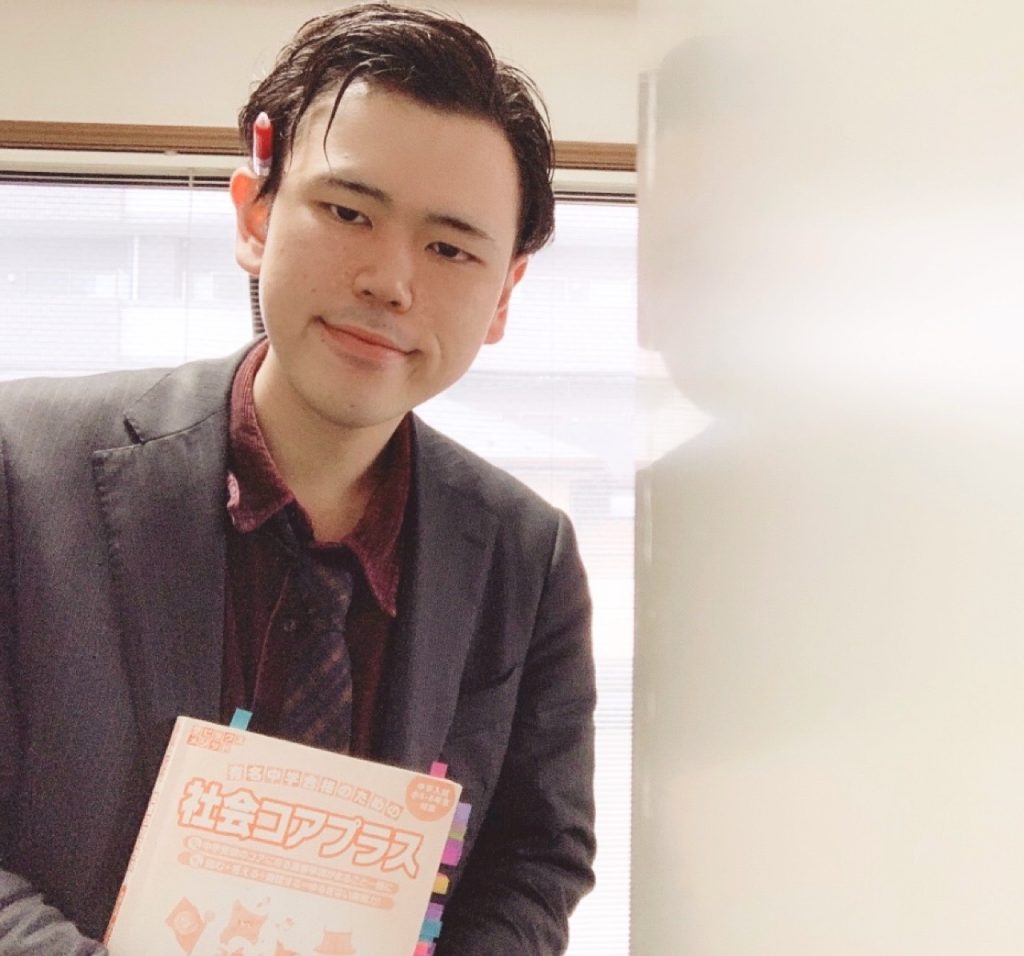中学受験の算数で最上位レベルになるために、プロ家庭教師がお伝えする【4つの習慣】

こんなお悩みありませんか?
- 中学受験、算数のレベルが志望校まであと一歩届かない
- 算数さえ成績が安定すれば塾の最上位クラスに入れるのに…
- 成績が良い時と悪い時の波が激しく、算数の出来が安定しない
- 難しい問題は解けるのに、簡単な計算や基礎問題でよく落とす
- ケアレスミスを何度も指摘しても、なかなか直らなくて不安
- 間違えた原因を本人が説明できず、算数の復習が形だけになってしまう
中学受験の算数を指導していると、理解力自体は申し分ないのに「あと一歩で最上位層に届かない」というお子さまは意外と多いものです。この記事では、中学受験の最前線で10年以上指導を行い続けたプロ家庭教師の視点から、算数の成績を安定的に上位へ引き上げる4つの方法を解説します。
こんにちは。
中学受験専門プロ家庭教師の佐藤です。
中学受験の算数指導を行っていると
「もう少しで最上位クラスに届く」
「志望校の合格ラインにあと一歩」
「理解力はバツグンなのに算数の模試結果が安定しない」
というお子さまを非常にたくさん目にします。
たとえば四谷大塚偏差値で60前後の実力があったり
SAPIXで偏差値55前後を獲得できるお子さまは
基本的な思考力がしっかりあり
難問にもある程度太刀打ちできる力を持っています。
それでも、模試やテストの結果が安定しない。
良いときは爆発的に点を取るのに、悪いときは凡ミスの連続。
こうなってしまうと
「うちの子は本当に中学受験で失敗しないだろうか」
「どこかで大きく成績が落ち込む日が来てしまうのではないだろうか」
と保護者さまが不安になってしまうのみならず
お子さま自身も、せっかく一生懸命頑張っているのに
上下する成績に感情を左右されて、自信をなくしてしまうことも起こりえます。
私自身、12年間プロ家庭教師として中学受験の現場に立ち続けているので
そういったご家庭には多数出会ってきており
みなさまが抱くご不安は痛いほど実感しています。
もしかしたら、あなたのご家庭でも
お子さまが同じような状況に立たされているかもしれません。
しかし、プロ家庭教師として中学受験をするお子さまを長年見ていると
そうした「あと一歩層」には明確な共通点があります。
それは決して才能やセンスの問題ではありません。
正しい算数の攻略法を知っているか、いないか
それが「最上位層」と「あと一歩層」の違いだと
私は認識しています。
裏を返せば、あなたのご家庭でも
これからお話しする4つの「算数学習法」を意識していただければ
算数の実力を最上位層レベルまで引き上げることは十分可能です。
今回の記事では
「実力はあるのに算数の成績があと一歩届かない」
といったお子さま、ご家庭向けに
中学受験算数の成績を高い水準で安定させる方法を
4つの視点から、ていねいにわかりやすくご紹介いたします。
どれも特別な裏ワザではなく
実践が難しいものでは決してありません。
中学受験の現場で最上位層が「当たり前」にやっていることです。
もしあなたのお子さまと中学受験最上位層の生徒に違いがあるとすれば
その当たり前を意識しているか・していないか
その違いでしかありません。
だからこそ、今日からあなたのご家庭でも実践できる学習の方法論だけを
ここではお話ししていきます。
「そもそも算数に苦手意識があって塾の下位クラスからなかなか上がれない」「中学受験でどこにも受からなそうで心配」といったご家庭もいらっしゃるかもしれません。【算数の基礎力を上げ、偏差値50を突破する方法】については、今後また別の記事で詳しくご紹介していきますので、引き続き当サイトをチェックしていただければ嬉しいです。
今回の記事が
中学受験を目指すあなたのご家庭にとって
価値のあるものとなりましたら幸いです。
それでは早速、
「中学受験算数の最上位攻略法」について
一緒に見ていきましょう。
【期間限定 公式LINEリニューアルキャンペーン】
中学受験プロ家庭教師監修
「親子げんかは悪くない」
公式LINE友だち追加で、無料で冊子を受け取ることができます
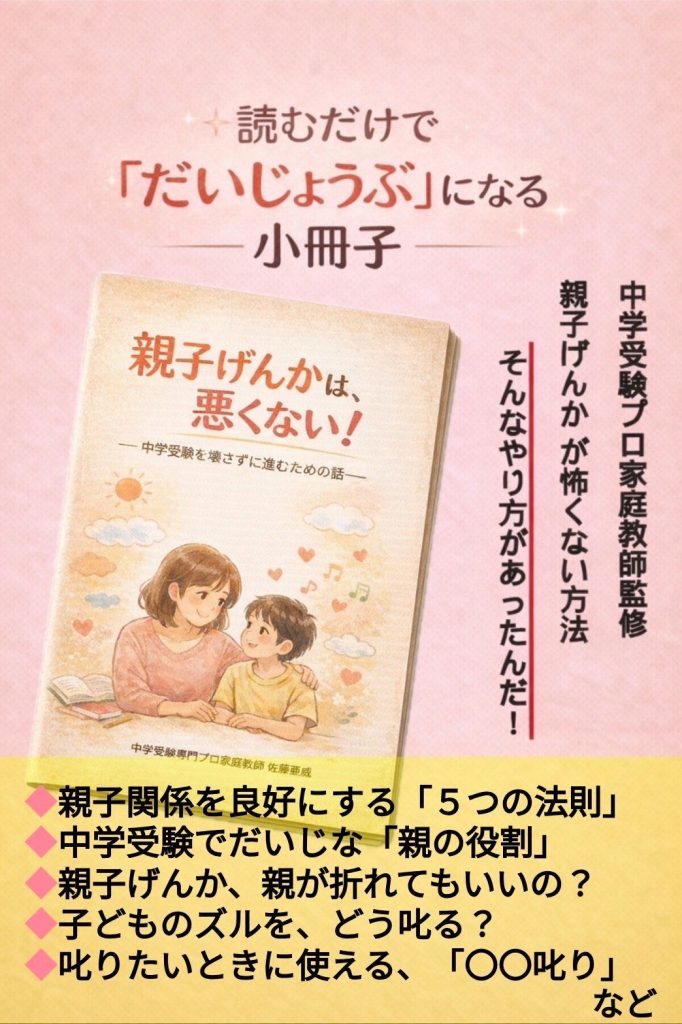
※LINEでは、「中学受験にまつわる不安や疑問をプロ講師に質問する」「保護者さま用中学受験ワークシートを受け取る」「登録者限定の特別価格体験授業・保護者さま面談に申し込む」「家庭教師の受講可能日程を確認する」など、様々な便利機能を無料でお使いいただけます。ご不要になった場合はブロックしていただくことで簡単に解除可能です。
算数の成績を最上位にする4つの方法① 比を制する者が算数を制す【プロ家庭教師が教える、中学受験の攻略法】
まず、中学受験算数の性質と、その中身を見ていきます。
中学受験算数は、大学受験数学とはまた違った特有の難しさがあると言われていますが
その原因の多くが、「比」の問題が頻出するためです。
じっさい、最上位校の算数を分析すると
圧倒的に多いのが**「比」を使う問題**です。
特に四谷偏差値65以上、SAPIX偏差値60を超える難関中学校の問題を見ると
算数は比のオンパレードと言っても過言ではありません。
理由は非常に単純明快で
比は「他分野と絡めやすい」単元だからです。
たとえば、
- 旅人算(速さ) × 比
- 食塩水濃度 × 比
- つるかめ算 × 比
- 売買損益 × 比
- ニュートン算 × 比
- 立体図形 × 比
このように、どんな分野でも比を絡めて問題を作成することができます。
したがって、
中学受験の問題作成者が算数の難易度を上げようとした場合
真っ先に活用するのが「比」単元です。
本来はあまり難しくない問題も、具体的数値を「比」に変えることで一気に難易度を上げることができてしまいます。だからこそ、算数の応用問題には「比」の考え方が高頻度で絡んできます。
こうなると、同程度の学力を持っている受験生同士でも
「比」が得意な受験生は算数で好成績が取れ
「比」が苦手な受験生は算数で伸び悩む傾向があります。
正直、「比を自在に使いこなせるかどうか」が
最上位層の分かれ目といっても過言ではありません。
一見すると「比の練習なんてもうとっくに終わってる」と思うかもしれません。
でも、実際には
「比の単元で、暗記した方法で問題が解ける子」
「あらゆる問題で、比を【考え方】として自在に扱える子」
では大きな差があります。
もし最近、あなたのお子さまが
比の問題演習を避けがちだったり
塾の演習で比の章をさらっと流していたなら
もう一度ていねいに見直してみてください。
比の理解を深くすることは、算数全体の得点力を底上げします。
「比」は、他の単元とは比べ物にならないほど
中学受験算数では重要な考え方です。
算数の成績を最上位にする4つの方法② 応用力と基礎力は「別軸の能力」【プロ家庭教師が教える、中学受験の攻略法】
「模試を受けると、大問1や大問2でミスが多発してるんです」
「そのくせ後半の難しい問題は解けていて」
「応用問題はできるのに、基礎問題で点を落とすんです」
家庭教師として算数のご指導を行っていると
保護者の方から、そういったご相談を受けることがとても多いです。
これは決して珍しいことではなく
むしろ算数が比較的得意な、「頭の良い子」に起こりやすい現象です。
なぜこのようなことが起きるのか、原因は、【①「算数基礎力」と「算数応用力」が別軸の能力であるにも関わらず】【②「あと一歩で最上位層」のお子さまは「算数応用力」強化の勉強ばかりする傾向にあるから】です。
多くのご家庭、ならびに受験生のお子さまは
「応用力は基礎の延長線上にある」
「算数の応用問題は、基礎問題が解けなければ太刀打ちできない」
と考えていらっしゃいます。
実はこの考え方は、半分正解で半分間違っています。
たしかに、ある一定のレベルに到達するまで、
すなわち中学受験の算数の内容理解がおおむねできるまでは
中学受験最上位校の入試問題のような応用問題を解くことができません。
しかし、たとえば四谷大塚偏差値で60前後、SAPIX偏差値で55前後の実力を持っているような
「算数の基本問題は一通り解けるようになった」受験生にとっては
「基礎力」と「応用力」は、まったく別次元の能力になります。
算数の「基礎力」と「応用力」とは
中学受験算数の「基礎力」
- 計算ミスを起こさない正確性
- 試験時間内に問題を解き切るスピード能力
- 「単位換算が合っているか」「不要な計算をしていないか」見直す能力
- 解ける問題に時間をかけ、難易度の高い問題は捨てるといった、取捨選択力
- たとえば自分で計算した結果「時速120kmで歩く」「お風呂のお湯を入れるのに6時間かかる」といった回答になった場合、その不自然さに自ら気がつく嗅覚
中学受験算数の「応用力」
- この問題にはどの解法を用いるべきなのか(ニュートン算? 場合分け? 植木算?)、問題に対するアプローチ方法を思いつく力
- 「なぜ六角形の内角の和は720度なのか」「なぜ等差数列の和は【(初項+末項)×項数÷2】で求まるのか」、公式の仕組みを自分で説明できる力
- 【比×売買損益】【場合分け×濃度】など、複数の単元を組み合わせて問題を解く力
このように、算数の基礎力と応用力は、そもそも方向性がまったく違う能力です。たとえるならば、応用力が「家の設計図を考える能力」だとしたら、基礎力とは「設計図通りに礎石を積む能力」「家を支えるための釘を、過不足なく正確に打つ能力」と言えましょうか。だからこそ、一定のレベルを超えた受験生にとって「応用ができるから基礎はできて当たり前」「応用問題の練習をすれば基礎の復習は不要」という理屈は通用しなくなってしまいます。応用問題はできるのに基礎問題で失点してしまう受験生が多い理由です。

したがって、「応用力」が高くても「基礎力」が低い受験生も存在するのです。
ここまでで
中学受験算数における「基礎力」と「応用力」は別次元の能力だとお話してきましたが
とりわけ、頭が良くて算数のセンスが高いお子さまほど
塾や宿題で難関校の入試問題を扱ったり、
日常学習で応用問題ばかり取り組んでしまうため
「応用問題は解けるのに基礎力が不足してしまう」
といった傾向に陥りやすくなります。
お子さまの性格によっては、「今さら基本問題の勉強なんて馬鹿らしい」「基礎問題集を解くなんて、勉強ができないみたいで恥ずかしい」といった理由で、基礎演習に取り組まず応用問題ばかり解きたがるといったケースもあります。環境的・心理的側面から【応用力ばかり伸びて基礎力が不足する】ことにより、結果的に算数全体の成績が落ちることは、非常によくあるスランプ例です。
もしあなたのお子さまが、算数の成績で伸び悩んでいたり
最上位レベルまであと一歩のところでつまづいていたりするのであれば
まずは模試や普段の小テストの回答を参照し
基本的な問題での失点をしていないかチェックしてみてください。
そのうえで、たとえばSAPIXなら毎日の『基礎トレ』を
四谷大塚なら『四科のまとめ』といった基礎問題集を
全問完璧に解けるまで徹底的に繰り返してください。
基本的な問題への取り組みをおろそかにせず
コツコツと取り組めるようになれば
「計算の精度」
「条件の整理」
「式の正確さ」
といった部分で格段にミスを減らせます。
中学受験算数における応用力と基礎力は、まったく別の筋肉です。
だからこそ、「応用ができるから基礎は大丈夫」と思い込まず
基礎演習を“別トレーニング”として積み重ねることが大事です。
塾の志望校別特訓時期や、受験期直前期間になっても
基礎問題トレーニングは継続して行っていくこと。
また、もしお子さまに「基礎問題」に対する心理的ためらいがありそうであれば
大人がていねいに取り払ってあげること。
そうすることで、正答にたどり着く前のミスを限りなくゼロに近づけていければ
算数の成績は安定しますし、実力的にも最上位層に確実に近づいていきます。
算数の成績を最上位にする4つの方法③途中式を書かない子は伸びない【プロ家庭教師が教える、中学受験の攻略法】
これもまた、最上位層まであと一歩レベルの受験生
すなわち、実力はあるのに成績が突き抜けない受験生に多いケースなのですが
途中式を書かないタイプのお子さまは
ある一定のレベル帯から先、成績が停滞していきます。
途中式を書きたがらないというのは、小学生あるあるだと思うのですが
そこにもお子さまなりの、さまざまな理由が存在します。
- 途中式なんて書いていると、時間がもったいない
- この程度のことは頭の中でできる
- 暗算で素早く解けないとかっこ悪い
- 単純に途中式を書くのがめんどうくさい
とりわけ、塾の中~上位クラスの算数授業では
先生方によって素早くスマートな解説がなされるため
自然と途中式を軽視してしまうお子さまも増えていきます。
しかし、中学受験の最上位校において
「途中式を書かない」というアプローチは通用しません。
なぜなら、途中式とは単なる計算過程ではなく
「自分がいま何をやろうとしているのか」
「どの単元の、何の解法で問題を解こうとしているのか」
といった複雑な思考を、”目で見てわかりやすくする”
算数における非常に便利なツールだからです。
私は家庭教師として指導をしている際、「途中式を書いた方が楽できる」「途中式を書いた方が絶対に速く解ける」と繰り返しお子さまに伝えています。頭のなかでごちゃごちゃ考えていると、時間もかかるしミスも増えるし、何より「自分が何をしているのか途中でわからなくなってくる」んです。途中式を書かないで問題に取り組むというのは、楽できる道具があるのにわざわざ使わず作業するのと同じこと。まして最上位レベルの算数で、途中式を書かないで回答を導くのはほぼ不可能です。
たとえばプロの小説家や脚本家だって
物語を書く前に必ずプロット(途中過程の下書き)を作りますし
建築家だって、家を建てる前に必ず設計図を作ります。
頭の中だけで作り上げたものを、そのまま形にする職人は滅多にいません。
なぜなら、自分の思考や途中過程を紙に書き出すことで
- 自分の考えを整理できるし
- 自分が何を、どこまで考えたのかを記録できるし
- 複数の考え方を同時並行して進められるし
- ミスが起きたら、「どこからズレたか」を紙面で追えるし
- 頭の中だけで考えるよりずっと楽できる
からです。
途中式とは、「正確に」「素早く」「楽に」中学受験算数を解くための道具です。
だからこそ、同じくらいのかしこさの受験生が何人かいたとしても
そのなかで、途中式を書く子は安定して難問を解き切ることができますし
途中式を書かない子は、途中で迷走してミスも連発してしまいます。
やはり、家庭教師として様々なお子さまの指導に携わっている身からしても、最上位層の子ほど、算数では几帳面に途中式を書いていますし、検算も自然に行っていますし、そのうえでハイスピードに問題を解き終えることができます。
「途中式を書いていると、その分時間がもったいない」と感じるお子さまもいらっしゃいますが
実際は、途中式をきちんと書くからこそ
「早く、確実に、楽に」算数の問題を解き切ることができます。
あなたのお子さまが、途中式を書きたがらない傾向があるならば
ぜひともこのことを、伝えてあげられたらと思います。
算数の成績を最上位にする4つの方法④ 「なぜ間違えたかを説明できる子」が最後に伸びる【プロ家庭教師が教える、中学受験の攻略法】
最後にもうひとつ
成績が最上位のお子さまに共通する習慣についてお話ししますが
これは算数に限らず、全ての分野に通じる力だと私は感じています。
それは「なぜ?」を自分の言葉で詳しく説明する力です。
たとえば、模試の結果を見て
”どうして間違えたのか”振り返ろうとしたとき
「ケアレスミス」としか言えない受験生は
その後も同じ失敗を繰り返すことが多いです。
対して、一度した失敗を繰り返さず、伸びていく受験生は
「単位換算でkmをいきなりcmに直そうとして失敗した。kmをmに直してからcmにするべきだった」
「筆算で246と書いたつもりが、”6″の文字を”0″に読み間違えて240と計算してしまった。字を雑に書いたせいで読み間違えた」
「A君の年齢を聞かれている問題なのに、B君の年齢を答えてしまった。登場人物が複数出てくる問題では、何を聞かれているのか最後にもう一度チェックするべきだった」
というふうに振り返りを行っています。
すなわち、成績が最上位層の受験生たちは
算数のケアレスミスひとつとっても
- 「自分が何の失敗をしたか」
- 「なぜ自分がその失敗をしたか」
- 「次に失敗しないためにどうすべきか」
を非常に細かく、自分の言葉で説明することができます。
とはいえ、最上位層の子たちが言語能力が特別高いわけではありません。
どちらかというと
「正解だったか、不正解だったか」ではなく
「どうして間違えたか」に強くこだわれるからこそ
同じ間違いをしないよう、しっかり言語化できるのです。
だからこそ、意識の持ち方次第で、どんなお子さまにでも取り組める習慣でもあります。「なぜ間違えたのか」「なぜこの回答を選んだのか」を、拙くても良いので自分の言葉で説明できるようになれば、自然と成績も向上していきます。
ご家庭でできる第一歩としては
テスト後に「どんな問題で時間がかかった?」「どういう問題で焦った?」と聞くこと。
答えを求めるだけでなく、言葉で自己分析を行わせてあげるだけで
お子さま自身、自分を客観視する能力が育っていきます。
ただし
「なぜ間違えたの?」
「なぜ時間内に解き終わらなかったの?」
と問いかけてしまうと、お子さまからすれば責められているように感じてしまうので
“責めてないことを先に伝える”
“なぜなぜ質問をしすぎない”
ことが、保護者さまにとっては大事になってきます。
子どもへの問い方のコツは、”共感から入ること”です。「この問題、お母さんだったら解き終わる自信ないなあ。A君とB君の年齢の部分、比が絡んでて混乱しそうだし。あなたはどこか不安なところあった?」というふうに、”私でも失敗する”ということを保護者さまから先に伝えてあげると、お子さまも「なぜ難しかったか」「なぜ間違えたか」話しやすくなります。
いちばん大切なのは、失敗しないことではなく
失敗の理由を言語化し、自己分析ができること。
プロ家庭教師の指導現場でも、成績が安定する子ほど
やはりこの自己分析が深いです。
自分の癖・得意・弱点を言語化できるようになると
学習効率は格段に上がっていきます。
さいごに:算数の最上位層は「一歩立ち止まって考える」【プロ家庭教師が教える、中学受験の攻略法】
ここまでお伝えしてきた四つの視点は
それぞれ別の話のようでいて、実は一本の線でつながっています。
共通しているのは、「一歩立ち止まって考えること」
- 算数の解法の一つとして、「比」を本当に使いこなせているか
- 応用だけでなく、ちゃんと基礎力も備わっているのか
- 途中式を書いていくなかで、自分の考えがしっかり整理できているか
- 間違えたときに「なぜそうなったか」を言葉にして、考えを振り返ることができるか
中学受験の算数で最上位の成績を取れる受験生は
これらを当たり前の習慣としてこなしています。
ただし、ここから特に大事なことなのですが
「いきなりすべてを完璧に仕上げようとはしないこと」
これはご家庭でも意識していただければと思います。
というのも、ここまでお話ししてきた通り
- 基礎問題をあまり解きたがらない理由
- 途中式を書かずに問題を解こうとする理由
- 自分の間違いを振り返りたがらない理由
ここには、間違いなくお子さまなりの心理的要因があります。
「今さら基礎問題の練習なんてかっこ悪い」
「途中式なんて書くより、一発で答えを出す方がスマートっぽい」
「テストの間違いを家族で振り返るなんて、親に責められているみたいで嫌だ」
私もプロ家庭教師として中学受験の現場に数多く携わってきましたが
小学生のお子さまだからこそ
理屈ではわかっていてもなかなか実践できない事柄もあります。
だからこそ、大切にしていただきたいのは
「お子さまの気持ちも踏まえつつ、算数の取り組み方を伝えること」
「少しずつ、確実に一つ一つのことを実践すること」
たとえば、
- 毎日10分だけでも「基礎トレ」や「四科のまとめ」を完璧に解ききる
- 週に数問は「比×速さ」「比×濃度」など、異なる単元を組み合わせた問題に挑戦する
- 解くときは、3問に1問だけでも途中式を丁寧に書く
- テスト後は、間違いの中から3つだけ選んで「どうして間違えたのか」をメモする
こうした“小さな習慣”を続けていくと、数週間もすれば
「ケアレスミスが減ってきた!」
「問題文の意味をすぐつかめるようになった!」
といった変化が出てきます。
そしてお子さま自身が達成感、自己肯定感を持てるようになれば
中学受験の難しい算数問題にも
あらゆる角度から、十分太刀打ちできるようになります。
最上位層の子たちは、けっして特別な才能があるわけではありません。
比を意識し、基礎をおろそかにせず、途中式で考えを整理し、自分の間違いを丁寧に振り返る――。
この当たり前を、何より地道に、何度でも繰り返しています。
今日からの小さな一歩で大丈夫です。
「一歩立ち止まって考える力」を育てる習慣が、算数を安定して強くする。
その積み重ねが、最上位層への一番確実な道です。
とはいえ、「どうやって子供に声をかけていいかわからない」「中学受験の算数について親でもわからないことが多い」「今回読んだ内容以外にも、つまづきを抱えているように思える」といったお悩みを抱えている方も多いかと思います。もしあなたがそういったお悩みを抱えていらっしゃるならば、ぜひ一度、私どもにもご相談ください。私、佐藤はプロ家庭教師として現在もたくさんのご家庭のお手伝いをしております。算数という科目に限らず、他科目の取り組み方や中学受験全般についてもお話しできることがございますので、あなたやお子さまが抱いているご不安・相談したいことなどがれば、ぜひお気軽にお声がけくださいね。ご相談等はこちらのリンクから無料登録できる公式LINEから行うことができます。
過去の人気ブログ記事はこちらからもお読みいただけます
それでは今回の記事
『中学受験の算数で最上位レベルになるために、プロ家庭教師がお伝えする【4つの習慣】』は以上とさせていただきます。
また次回の記事でお会いしましょう!
【期間限定 公式LINEリニューアルキャンペーン】
中学受験プロ家庭教師監修
「親子げんかは悪くない」
公式LINE友だち追加で、無料で冊子を受け取ることができます
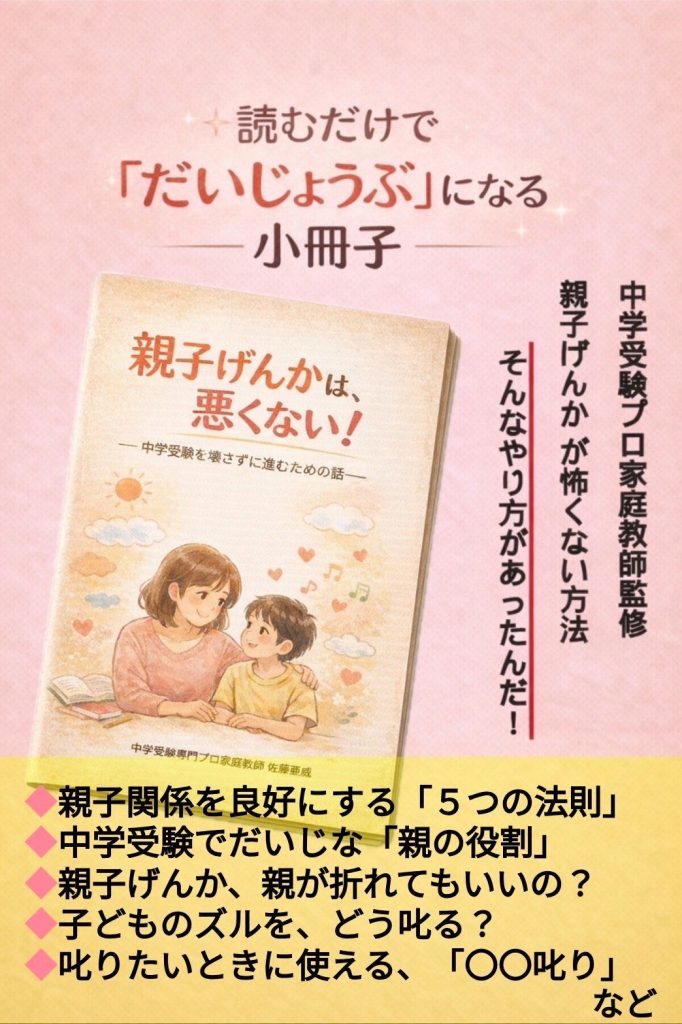
※LINEでは、「中学受験にまつわる不安や疑問をプロ講師に質問する」「保護者さま用中学受験ワークシートを受け取る」「登録者限定の特別価格体験授業・保護者さま面談に申し込む」「家庭教師の受講可能日程を確認する」など、様々な便利機能を無料でお使いいただけます。ご不要になった場合はブロックしていただくことで簡単に解除可能です。
この記事を書いた人